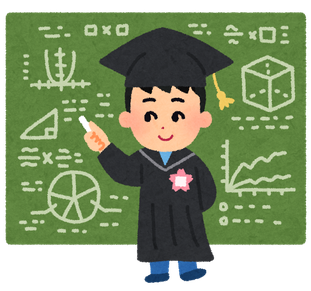
当方「地頭錬成法」と銘打ってブログを書いていますが、今回は地頭とは一体何なのかということについての私の意見を述べたいと思います。
地頭が良い人はデキる人
一般に「地頭が良い」とはどういうものと受け止められているでしょうか。
何だかんだで仕事ができたり成績が良い人間のことを指すことが多いようです。東大や国立の医学部に合格するには地頭が良くないと無理、というような話は枚挙に暇がありません。
一方で世間では、「地頭=学歴や成績の良さ」だけで受け止められてはいません。むしろ学歴や学生時代の成績は大したことがないにもかかわらず、仕事はとても良くできる人に対して「地頭が良い」という評価がなされます。その場合「地頭が良い」の前に「(学歴はないけれど)」が暗に示されることが多いように感じます。
いずれにしても「地頭が良い」というのはデキる人間であることが条件です。学歴ばかり高くて仕事が出来ない人には決して使われません。
社会に出てみればしばしばそういう人間に出会います。本当に東大出身なのかという人はたまにいますし、やぶ医者に至ってはなかなかの頻度で遭遇します(何人か頭に浮かびませんか?)。
彼らは、勉強はできるけど実務能力に欠ける、というような悪口(事実?)を言われることになるのですが、苦労して勉強してきたのにそんな目にあうのはちょっと気の毒です。
せっかく勉強をするのでしたら、やはり「地頭が良い」と言われる存在になりたいものです。ましてやこれからは実力の問われる厳しい社会になります。学歴だけでは生き残ることは困難です。
それでは具体的に、地頭が良い条件について検討していきます。
高い理解力
一番重要な条件は何と言っても物事を理解する力です。理解力があれば、他の人から言われたことを消化して実行したり、マニュアルや要望書を読み込んで円滑に業務を遂行することができます。相手の側からすれば、理解力の高い人と話をするのはストレスが少なく物事がスムーズに進むので、当然高く評価されることになります。当たり前にあるべき能力のようですが、備わっていない人は案外多いと思います。
これは日本語ができれば何とかなるというものではありません。外部からの情報を噛み砕いて自分の腹に落ちるように消化するにはいくつかの手順を習得しておく必要があります。大きなものを3つ挙げます。
まずは論理力。筋道を追っていくときの法則です。これに則っていれば、対話相手の言うことや、企画書・提案書等に書かれている内容の要旨をつかみやすくなります。それだけでなく話の展開を予想しやすくなるので、素早く理解することにもつながります。
次に俯瞰力。論理でまとめられたひとつひとつの話題を、大きな視野で見ることの出来る能力です。全体像をつかむことで理解が一層深まります。
そして知識もやはり必要です。論理による予測で補うこともできなくはないですが限界があります。知識はいくらあっても困ることはありません。
論理、俯瞰、知識。この3つをベースにした理解力が、地頭の良さの大黒柱と言えます。地頭が良いと言われる人は高確率で持っている力です。
発信力
発信力は自分の意見や考えを伝える力です。これは理解力に加え、自ら組み立てていく力である構想力も必要になります。さらには、伝える相手によって話のレベルの上げ下げをしないといけないこともあり、人を見る観察力やその場の対応力も問われます。身につけるのはなかなか骨の折れる作業です。
そしてこれは、集団の和を重んじてきた日本人にはとても苦手な分野です。出る杭は打たれる文化ですから仕方がなかった面があります。
ところが現在は一昔前よりもずっと重要になってきました。終身雇用制度の衰退に伴う実力主義・成果主義の台頭や、個人主義の色の強い欧米的グローバル化を社会が取り入れることにより、発信力を持たないと埋もれてしまう危険性が増したからです。
そのグローバル化に伴い英語の必要性も増していますが、聞いて読むだけではなく、speaking、writingといった発信力も問われ始めています。今のところ企業ではTOEICL&Rのスコアが大きな指標ですが、早晩S&Wのスコアも併せて要求されることも増えるでしょう。
ディベートを授業に取り入れる学校なども出てきてはいますが、まだまだ一般的とは言えません。しかし、PowerPointやKeynoteなどのプレゼンソフトの普及により発表する機会は増えています。討論好きの外国人との国際的な交渉も今後は避けられません。もはや伝えることが得意ではないと言っていられる場合ではないのです。
だからこそチャンスです。日本人は不得手だからこそ、普通に発信力があるだけで相対的に優位に立てるのです。ちょっと基本を押さえるだけで一目置かれてお得です。正直なところ日本人は交渉下手となめられているので、骨のあるところを見せて存在感を高めてほしいですね。
優れた記憶力
記憶力が良い人は地頭が良い確率が非常に高いと考えられます。というのも、私がこれまでに出会ってきた知識の豊富な人は例外なく出来る人だったからです。
詰め込み学習や丸暗記が批判されるようになって久しいですが、その影響で記憶力の良さは割を食ってきた感があります。「あいつは知識ばかりの頭でっかちで、応用が効かない」などという話は結構昔から耳にしてきました。でもそれは当てになりません。中にはそういう人もいるというだけで、レアケースと考えて間違いないと思います。
理解力がある人は、ある物事を記憶するときに、その背景や筋道、つまり文脈を考えます。文脈の中で覚えた物事は忘れにくくなります。ひとつひとつの事柄が複合的に絡まり合い、互いに記憶のフックとなるからです。
これが逆に、個々の事項だけを覚えて全体のつながりを見ていない人がいたらどうでしょう。その人はその物事の全体の流れを他人に伝えることは難しいでしょう。この状態を指して「知識ばかりで応用が効かない」というのでしょう。
しかし大量の記憶を保持できている人は、それらの記憶同士が相互に絡まって全体が見えてくるかもしれません。断片にしか向いていない意識を変え、全体に広げるだけで一気に変わるかもしれません。つまり、覚醒の一歩手前であり隣り合わせの状態なのです。これは量が質に転換する一例と考えます。だから、そう低くはないであろう可能性に託して記憶力の訓練はしておくべきと思います(特に子供のうちは)。
理解力のところでも触れましたが、知識は理解力を重要な要素です。あって困ることはありません。それにそもそも博学というだけでも一目置かれるべきです。クイズが得意な人は無条件にすごいじゃないですか。試験を記憶力だけで乗り切った人は小馬鹿にされ、クイズ王は尊敬を集める。これは矛盾しています。よって、記憶力を鍛えることにデメリットはないと考えます。
頭の回転が速い
どんな話をしていても立て板に水で返してきたり、予想外の発想で皆を驚かせてくれる。そんな頭の回転が速い人こそ、地頭が良い人というイメージにピッタリです。
頭の回転の速さは、これまでに見てきた理解力・発信力・記憶力がそろって初めて成り立ちます。会話においては、相手の話を的確に処理していき、記憶の引き出しを検索しつつ素早くまとめ上げて発信する。こんな構造です。付け加えるなら、速く反応する訓練はしておく方が良いでしょう。
討論や交渉に臨むときは事前に用意周到に準備するのですが、不測の事態も頻繁に起こります。そんなとき、時折何かが頭の中に降りてきたかのようにひらめくことがあります。その場では気持ちが高ぶっているので神懸かっていたとか天啓だとか思ってしまいますが、後々振り返ってみると、用意してきたことの組み替えだったりします。準備の段階で内容を深く理解していたからこそ出てきたものですし、そこに自らの経験や記憶が加わったからこそ出たひらめきです。何もないところからひらめくなんて虫のいい話はそうそう転がっていません。ただ、それがその場でひらめいた瞬発力は運の良さもおおいにあったと思います。
気をつけたいのは、反応が速いことにあまり固執してはいけないことです。なんでもかんでもレスポンスの速さばかり求めると熟考しなくなるからです。より大事なことは最終的な結論のレベルが高いことです。そのためには考え抜く方が良い結論に至ることが多いでしょう。タイムリミットがあるなら仕方ありませんが、そうでなければより良い答えを求めるべきです。必要以上に頭の回転の速さを追求すべきではありません。
まとめ
- 地頭が良い条件として、理解力を一番重視している
- 発信力は理解力が派生したもので、今後さらに要求される
- 記憶力は理解力の覚醒につながりうる
- 記憶力が良いことはもっと評価されて良い
- 頭の回転の速さは理解力・発信力・記憶力の上に成り立つ
- 頭の回転の速さを求めすぎるのは良くない
コメントをお書きください